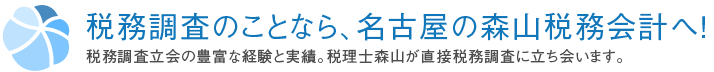【セカンドオピニオン】
セカンドオピニオンとは、よりよい判断をおこなうために当事者以外の専門的な知識をもった第三者に意見を求めることです。
いわゆる大手企業では事業運営上の様々な問題に複数の税理士が対応しておりますが、中小企業では原則として顧問税理士一人が全て問題を処理しております。より適切な経営・税務判断をおこなうためにも、今後は中小企業でも複数の税理士を利用することが望ましいと思います。
なお、このサービスは、あくまでも現在の顧問契約を変更される必要はございません。現在の顧問税理士と良好な関係を維持したうえでご利用いただけます。
【対象者】
- 他の税理士の意見を聞いてみたい。
- 顧問税理士に発言する前に、その内容を事前に確認してみたい。
- 顧問税理士からの返答が遅い。
- 担当者が税理士ではないので、税理士に聞いてみたい。
- 決算は顧問税理士に、相続は別の税理士に相談したい。
- 顧問税理士は高齢であるため、若手税理士に相談したい。
【サービスの流れ】
ご相談
ご相談を受け、どのような提案ができるか説明させていただきます。
サービス内容の打ち合わせ
貴社の課題に対し、適切なサービス内容を決定致します。
ご契約
決定したサービス内容に関し、契約書を作成致します。
サービス開始
ご契約日の翌日からサービスを開始致します。
【料金】
Aプラン
顧問
月額22,000円~
Bプラン
1案件のみのご相談
電話、メールでの回答 5,500円~
文書、レポート作成を必要とするもの 11,000円~
【税額計算における処理方法の選択基準例(セカンドオピニオン対象事例)】
<個人事業か法人かの選択>
所得金額が大きくなれば当然法人の方が有利となりますが、それほど大きくない場合でも、法人では家族従業員に対する給与や家族に対する賃借料・支払利子が認められているので税務上は有利となります。
<法人成りの選択>
法人では代表者に給与を支給することができるため、年間の利益金額が約700万円程度を超えると、法人成りに税務上のメリットを生じます。
<創立費及び開業費の繰延べ>
創立費や開業費は、その全額を設立第1期目の費用とすることもできますし、繰延資産として計上しておいて第2期目以降に随時に任意の額だけ償却することもできます。
<収益計上における検収基準の適用>
棚卸資産の販売による収益の計上は引渡基準により行いますが、引渡の時点はいくつかありますので、その中でもっとも有利なものを選択することができます。
通常の棚卸資産については、出荷基準か検収基準によりますが、一般的には検収基準を選択すると有利になります。
<決算締切日の利用>
売上及び仕入は事業年度を単位として計算し、それに基づいて所得金額及び税額を計算するのが原則ですが、一定の条件により決算締切日を単位として計算することも認められています。
<委託販売における売上計算書到達日基準>
委託販売については、受託者が販売した日に収益を計上するのが原則ですが、売上計算書が到達した日に収益計上することもできます。
<工事進行基準の適用>
建設工事等の収益の計上は完成基準により行うのが原則ですが、長期の工事については工事進行基準を適用することもできます。
工事進行基準は発生主義による収益計上ですので、一般的には淵となりますが、早めに収益を計上したいときや利益を平準化したいときには選択の余地があります。
<長期割賦販売等における延払基準の適用>
長期割賦販売等であっても、引渡基準により収益を計上するのが原則ですが、特例として延払基準により収益を計上することも認められています。
<売上割戻しの計上時期の選択>
売上割戻しの計上の時期については、その算定基準のあり方等によって、販売日基準、通知日基準又は支払日基準が定められていますが、販売日基準が選択できると有利になります。
<棚卸資産の付随費用の処理>
棚卸資産に係る付随費用は取得価額に算入するのが原則ですが、購入代価又は製造原価の3%以内であれば費用処理することができます。
また、棚卸資産たる土地の取得又は保有に係る租税公課等についても、法人の選択により費用処理することができます。
<棚卸資産の評価方法の原価法における選択>
棚卸資産の評価方法として個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、最終仕入れ原価法、売価還元法の6種類の方法が定められていますので、そのうち最も有利、かつ各法人に適した方法を選択する必要があります。
<棚卸資産の評価方法として低価法の適用>
原価法では棚卸資産の評価損は原則として認められませんが、低価法を採用すれば時価の下落による棚卸資産の評価損を計上できることになります。
<製造原価に算入する費用の選択>
生産に関連して発生した費用のすべてを製造原価に算入する必要はなく、適正な原価計算の基準に基づいて判定することにより、期間費用として処理することができる費用もあります。
<原価差額の調整における選択>
原価差額が総製造費用の1%以内であれば、期末棚卸資産への配賦をしないで期間費用とすることができます。
この場合、総製造費用の1%を超えるかどうかは、事業の種類ごとに判定するのが原則ですが、製品の種類又は工場ごとに判定することもできます。
<定率法の適用>
主な減価償却の方法としては定率法と定額法がありますが、定率法の方が早期償却が可能なので有利です。
<少額減価償却資産の購入>
減価償却資産は固定資産に計上し耐用年数にわたって償却するのが原則ですが、10万円未満のもの及び使用可能期間が1年未満のものについては一時償却することができます。
<20万円未満の減価償却資産の購入>
減価償却資産は固定資産に計上し耐用年数にわたって償却するのが原則ですが、20万円未満のものについては3年で均等償却することができます。
<減価償却資産の取得に伴う租税公課等の処理>
減価償却資産の取得価額には、その取得に関連して支出するすべての費用を算入するのが原則ですが、租税公課等は取得価額に算入しないで費用として処理することができます。
<修繕費となる範囲内での修理・改良>
固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その資産の使用可能期間を延長させる部分又は価額を増加させる部分は、資本的支出としてその資産の取得価額に算入しますが、それ以外のものは修繕費として費用処理することができます。
<有姿除却の適用>
減価償却資産の除却損は、現実にその資産を廃棄処分したときに計上するのが原則ですが、その使用価値が尽きていることが明確なものについては、現状有姿のまま除却損を計上することも認められています。
<役員に対する定期同額給与等の支給>
役員に対する給与のうち定期同額給与等は損金に算入されますが、それ以外のものは損金不算入となりますので、役員に対しては定期同額給与等を支給すると有利になります。
<役員に対する事前確定届出給与の支給>
役員に支給する給与のうち、増額支給の役員給与(いわゆる役員賞与)は損金不算入となるのが原則ですが、事前に税務署に届出をするなど一定の要件を満たすものについては損金に算入されます。
<使用人兼務役員の選任>
役員に対する給与は定期同額給与等を除き損金不算入となりますが、使用人兼務役員に対する給与は、使用人分として支給する部分が損金に算入されます。そのため、取締役は使用人兼務役員とした方が税務上は有利となります。
<役員の分掌変更等による退職給与の打切支給>
役員に対し退職給与という名目で支給したものでも、現実に退職していない場合には、役員賞与として損金不算入となるのが原則です。
しかし、常勤役員が非常勤役員になったときなどに打切支給したものは、退職給与として損金に算入することができます。
<売上割戻しと同様の基準による少額物品の交付>
売上割戻しと同様の基準であっても、物品の交付や旅行等への招待は交際費等とされるのが原則ですが、単価が3,000円以下の少額物品の交付は売上割戻しとして処理することができます。
<渡切交際費の活用>
交際費等は原則として損金不算入とされますが、渡切交際費を支給すれば給与として損金に算入することができます。
<一人当たり5,000円以下の飲食費>
接待等のために支出する飲食費は交際費になるのが原則ですが一人当たり5,000円以下の飲食費は交際費の範囲から除外されて、その全額が損金に算入されます。
<契約に基づく情報提供料等の支払い>
情報提供等を業としない者に対して支払われる情報提供料等は、交際費等とされるのが原則ですが、契約に基づくものであることなど一定の条件を満たす場合には交際費等には該当しません。
<社葬の費用>
葬儀の費用は個人で負担するのが原則ですが、法人の役員等が死亡した場合、社葬を行うことが社会通念上相当であり、かつ社葬のために通常要すると認められる金額については、法人の損金に算入することができます。
<社宅の利用>
役員や従業員が社宅を利用した場合の経済的利益については、給与として課税されるのが原則ですが、一定額以上の家賃を徴収している場合には非課税とされます。
それを負担した法人では福利厚生費として処理することができます。
<子会社等の設立>
子会社等の設立は、本来、経営の効率化等を目的とするものですが、軽減税率の二重適用、交際費等の損金算入限度額の拡大、特定同族会社の留保金課税の軽減などの節税効果もあります。
<被合併法人の欠損金の引継ぎ>
被合併法人の欠損金を合併法人に引き継ぐことは認められないのが原則ですが、適格合併の場合には、欠損金を引き継ぐことが認められます。ただし、その引継ぎには制限が設けられています。
【サービスのお問い合わせ】
お電話でのお問い合わせ、または、24時間対応の相談予約フォームよりお問い合わせください。